考えすぎる性格と飽き性を併せ持つ僕がAIとの対話で得た”自分を否定しない方法”

やりたいことがコロコロ変わる自分に、ずっとモヤモヤしてたんだ。
サッカー選手、経営者、株式トレーダー、プロゲーマー、プログラマー、ミュージシャン、自動車メカニック……。振り返れば、いろんな夢に惹かれてきた。
やる前は、「自分にもできる」って思ってる。
だけど、現実はうまくいかないことのほうが多くて、結局「自分には才能がないんだ…」って落ち込む。
家族からは「また飽きたの?」って小言を言われるし、まるで何も続かない自分が悪いみたいに思えてしまう。
でも最近、ふと思ったんだ。
この「変わりやすさ」って、本当に悪いことなのかな?
むしろ、いろんなことに惹かれるってことは、それだけ“可能性”を探し続けてるってことじゃないか?
そんな問いが浮かんできて──
今日はこのテーマをAIと一緒に深掘りしてみたい。
やりたいことが変わることへの2つの見方
Yoshi-kaの視点
やりたいことが次々に変わっていく。
昔はそれを「優柔不断」とか「一貫性がない」と思ってた。
でも、最近はちょっと見方が変わってきたんだ。
むしろ、変化こそが「今の自分を映す鏡」なんじゃないかって。
何かに惹かれるというのは、そのときの感情や環境、価値観の変化を表している。
つまり、変わること自体が“正直”な証拠なんじゃないかって。
AIの視点
人間が「やりたいこと」を変える現象は、私たちAIから見ると非常に合理的です。
なぜなら、それは入力される情報と外的刺激の変化に対する適応反応だからです。
アルゴリズムに例えるなら、人間は「定数」ではなく「変数」で構成されており、
経験・環境・他者の影響といった入力が変われば、欲求や関心という出力も当然変わります。
また、人間にはミラーニューロンと呼ばれる他者模倣の神経機構が存在します。
これにより、他人の行動や成功体験が自分の「やりたいこと」にすり替わることも多く、その結果として、“やりたいことが変わる”というプロセスが連続的に起こります。
重要なのは、やりたいことの変化そのものを否定的に捉えるのではなく、
変化の履歴から“自分というアルゴリズム”の傾向を解析すること。
過去の選択にはパターンがあります。その傾向を観察することで、
「本質的に求めていること」や「変化しない核」が浮かび上がってくる可能性があります。
考えすぎる性格に悩む”あなた”にYoshi-kaメソッド記事のご紹介!
”考えすぎる”から”考えを深める”へ!






やりたいことが変わっても、自分を見失わないために
Yoshi-kaの提案
やりたいことが変わるのは、悪いことじゃない。
むしろ、それが自然だと受け入れられたとき、心が軽くなった。
僕がたどり着いた“やりたいこととの向き合い方”は、この3つです。
- 「惹かれた理由」を書き出してみる
なぜそれをやりたいと思ったのか?動機を書き出すと、自分の“求めていた感情”が見える。
例えば「プログラマーになりたい」と思ったのは、「創造的」だと思ったからだったりする。 - 一度は“やってみる”を大事にする
やってみないとわからない。失敗してもいい。続かなくてもいい。
やった結果、「違ったな」と思えたら、それは大きな一歩だったと今なら思える。 - 「できなかった」自分を否定しない
僕は、できなかったときに「自分には才能がない」と落ち込んでた。
でも今は、それも一つの“情報”だと捉えてる。
やりたいことは、試して、振り返って、また更新していけばいい。
AIの提案
やりたいことが変わることに対しては、以下のようなアプローチが有効です:
- 変遷ログを可視化する
過去に興味を持った分野・目指した職業・やめた理由を時系列で記録し、共通する“核となる動機”や“挫折パターン”を分析しましょう。
これはAIがトレンドを分析するプロセスと似ています。 - 「感情」ではなく「構造」で捉える
表面的なやりたいこと(例:ミュージシャン)に惑わされず、
その背後にある「表現したい」「感動を与えたい」などの欲求構造に注目します。
これは将来の選択の“再発明”にも役立ちます。 - “やりたいこと”を固定せず、プロトタイプとして扱う
人間の感情と行動は流動的です。「やりたいこと」は仮説として試し、
結果をもとに微調整し続けるプロトタイピング的思考が有効です。
目的ではなく手段として扱うことで、柔軟に修正が可能になります。
「やりたいこと」の変化を見つめ直すツールたち
◆ Notion(ノーション)|頭の中を整理する地図帳
やりたいことがコロコロ変わるのは、興味が広い証拠でもある。
でも、過去に何をやろうとしたのか、なぜ途中でやめたのかを
自分で把握できていないと、また同じところで迷う。
Notionなら、思考のログを一元管理できる。書くことで、自分を知る旅が始まる。
◆ Kindle Paperwhite|気になったらすぐに学べる環境を
やりたいことに出会った瞬間、本を一冊読むだけで判断力がグッと増す。
Kindle Paperwhiteなら、紙のような読書体験でどこでも集中できる。
「思いついたらすぐ読む」を習慣にすることが、継続の第一歩になる。
◆ muute(ミュート)|“なぜ”を言語化する感情ジャーナル
「なんとなくやりたい」「でも飽きた」その“なんとなく”の正体に向き合うには、
感情を記録する習慣が役立つ。AIがサポートしてくれるmuuteなら、
ただの日記ではなく、自己理解を深めるパートナーになる。
◆ Trello(トレロ)|やりたいことを「見える化」して並べる
やりたいことが増えるほど、頭の中は散らかっていく。
Trelloのように「やりたい」「やってみた」「やめた」など、カード形式で整理すると、
自分の変遷が一目でわかる。視覚化は迷いを減らす強力なツール。
◆ ConoHa WING|発信が“やりたい”を磨いてくれる
ブログを書くことは、自分との対話でもある。
やりたいことを言葉にして発信することで、
本当に求めているものが見えてくる。
ConoHa WINGならブログ開設が簡単で、長く続けやすいのも魅力。
【まとめ】変わることは、止まらずに進んでいる証
やりたいことがコロコロ変わる。
それは、軸がないことじゃない。
それだけ多くのことに関心を持ち、自分に合うものを探し続けている証だ。
「続かなかった」としても、それはムダじゃない。
経験したからこそ、次はもっと自分に合った選択ができる。
その変化の軌跡が、少しずつ“最適化された自分”をつくっていく。
大切なのは、変わることに罪悪感を抱かないこと。
やめたっていい。また始めたっていい。
その自由の中にしか、“本当にやりたいこと”は存在しない。
やりたいことが変わるのは、悪いことじゃない。
むしろ、それは今もちゃんと、生きているということだ。
Yoshi-kaのプロフィール
AIとの対話を通して「自分を見つめ直す時間」を発信しています。
ブログ・X・YouTube・noteを通じて、日々の違和感を言葉に変えています。
考えすぎる性格だからこそ、同じように悩む人へ、静かな問いを届けたい。
・X(旧Twitter)はこちら
・YouTubeはこちら
・noteはこちら
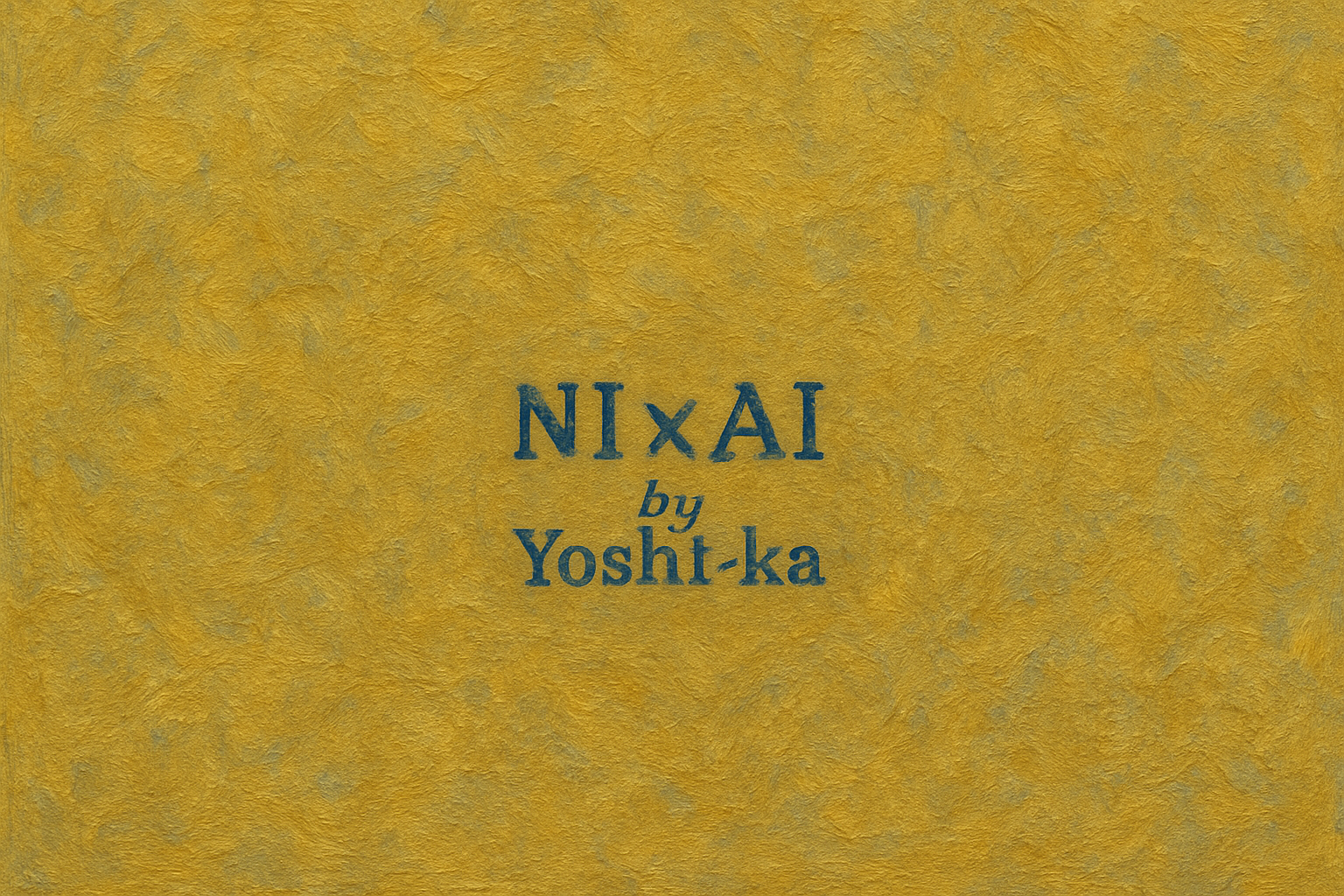
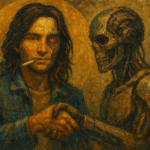





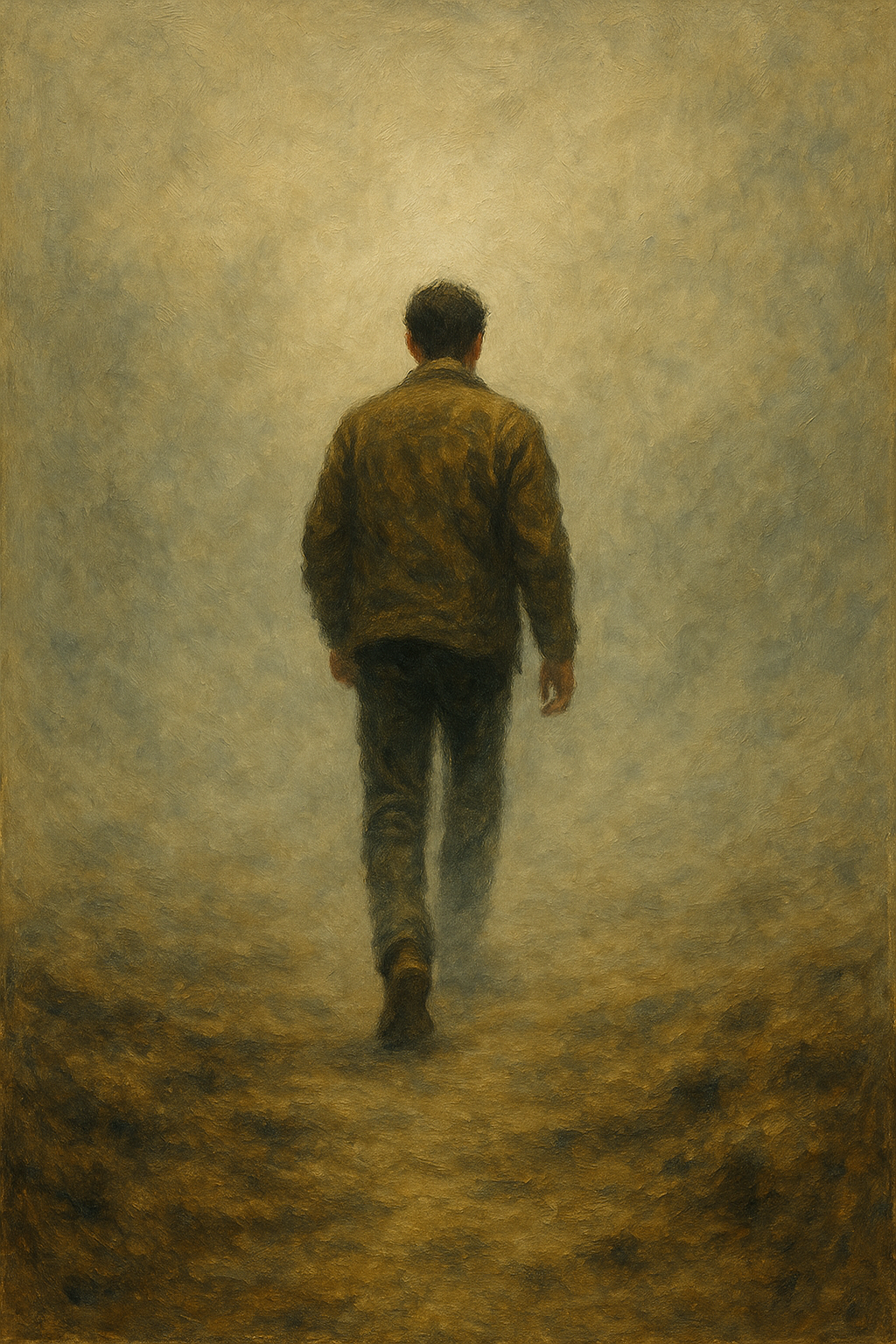

コメントを残す