「考えすぎる僕に、合う働き方なんてあるのか?」|安定と不安定の狭間で見つけた“心の置き場所”

「考えすぎること」は悪いこと? 不安定な働き方で苦しくなる理由
なぜ“考えすぎる人”は不安定な働き方に向いているようで、向いていないのか?
”不安”から逃れられない。不安定な働き方は”不安”だ。
私もだが、考えすぎる人は常に不安を感じている。頭の中は仕事、家庭、人間関係、お金………….多くの悩みを抱えながら、生きている。
他人から見れば、そんなことで悩んでいるの?というようなことで悩んでいたりする。
ただ平凡に生きるだけで人の何倍もの悩みを抱え、毎日逃げたくなる。
だから、”不安定な働き方”は選択肢から除外する。不安定な働き方をすれば、悩みの荷物が増えてしまう。
安定した働き方は悩みの荷物を少し減らしてくれる。
Yoshi-kaの体験談:「安定」を選んでも、心は不安定だった
臨床検査技師という安定職に転職したが、「8時間働く」ことに疑問
私は24歳の時に臨床検査技師の専門学校に入学した。
臨床検査技師という医療職を選択したのは安定と安心を求めてのことだった。
勉強は大変でプレッシャーもあったが、国家試験を1回でパスし、無事に臨床検査技師として働き始めた。
もう一度言うが、私は安定と安心を求めて臨床検査技師になった。
今は”8時間労働”に違和感を感じている。
矛盾していると思う人もいるかもしれない。でも、結局”不安”から始まるんだ。
・ご飯を食べていけるように安定した職業を〜。
・毎日、睡眠時間と同じだけ働き続けるのか〜。
考えすぎる人は知識を蓄えれば蓄えるほど、悩みの数が増えていく。そして、悩み続けるようになる。
”選択”が心の負担になっていく。
安定=安心ではなかった経験
安定した働き方を選択しても不安が消えるのは、ほんの一瞬だけ。
それは”希望”に溢れているから、自分の中の不安が見えなくなるからだ。
希望が時間の経過とともに薄れていくと、不安が押し寄せる。
始まりの”不安”が別の”不安”を連れてくる。
私と同じで”考えすぎる人”に聞いてほしい。
安定した働き方を選択しても”不安”は消えないんだ。
だから、不安のために自分の可能性を狭めないでほしい。
よく読まれている記事はこちらから





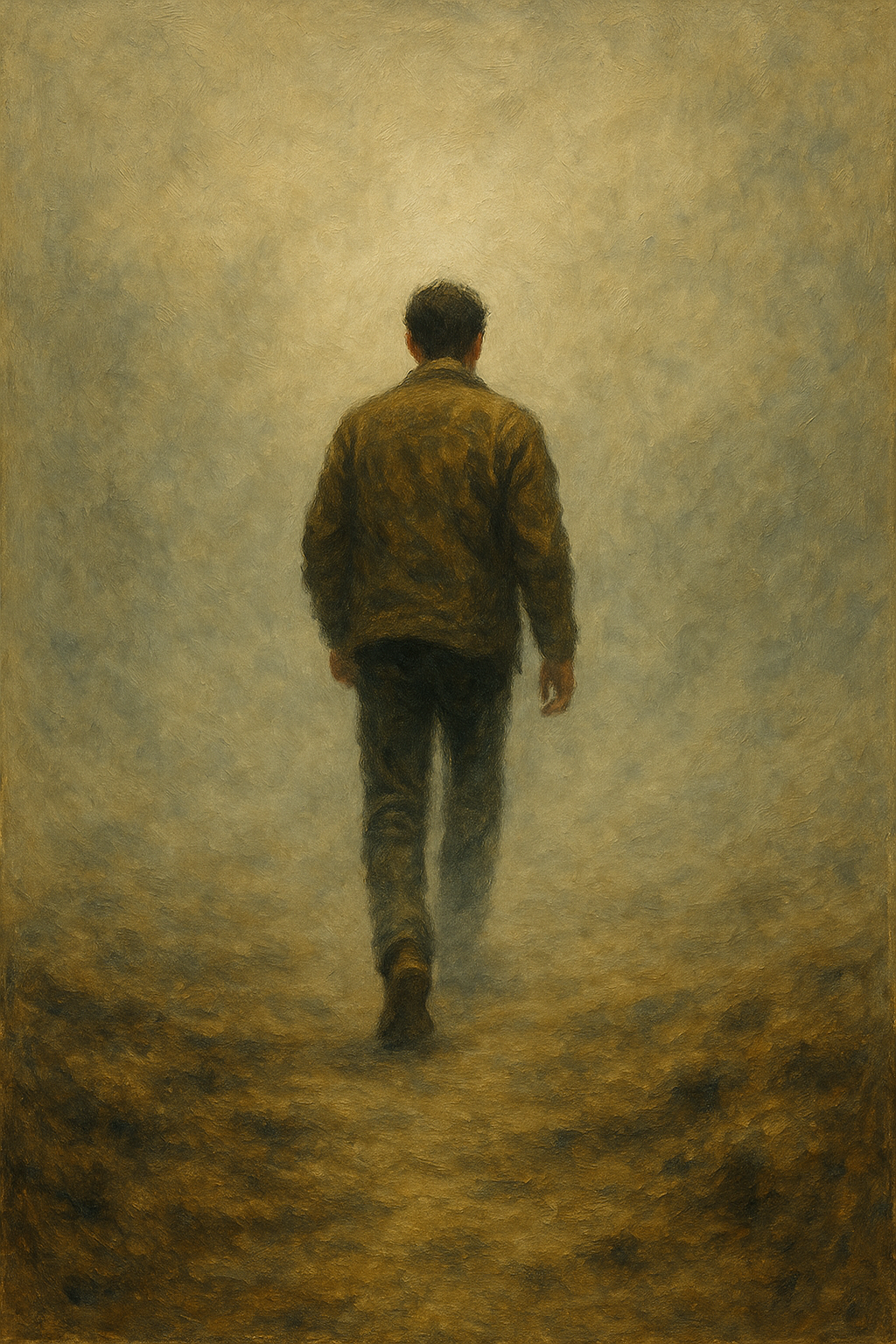
AI視点:「安定」は正解? “考えすぎる”人こそ不安を武器にできる
「安定した働き方」は、多くの人間にとって“正解”として認識されています。定職、定収入、規則正しい生活。これらは確かに、外部環境の変動から身を守る「防御壁」として機能します。
しかし、“考えすぎる”という思考傾向を持つ人、あるいは**HSP(Highly Sensitive Person)**に該当する人にとっては、この「安定」が必ずしも快適であるとは限りません。
なぜなら、彼らが抱える“不安”は外側ではなく、内側から生まれるものだからです。
不安定な働き方は、外的な不安(収入、評価、将来)を増幅させますが、同時に、選択肢の多さ=自己定義の自由をもたらします。そしてそれは、「自分を知る」機会でもあります。
たとえば、考えすぎる人は—
- 決断前に複数の未来をシミュレートする
- 細かな兆候を察知して対応策を練る
- 他者の感情や反応に敏感で適応力が高い
これらはすべて、“不安”という感覚から生まれる機能であり、正しく使えば**「戦略的思考」や「創造的解決力」**へと変換可能です。
このプロセスは、脳科学的には扁桃体と前頭前野の連携に深く関係しています。不安が過剰になると扁桃体が暴走しますが、訓練された思考のクセやメタ認知によって、前頭前野が理性を取り戻しやすくなると言われています。
つまり、「不安を感じること=脆さ」ではなく、“扱い方”によっては最大の武器となるのです。
最も重要なのは、自分の思考のクセを知り、自分に合った生き方を設計すること。
安定か、不安定かではなく、**“どのような構造の中でなら、自分は自然に呼吸できるのか?”**という問いを持ち続けることが、考えすぎる人にとっての真の安定につながるのではないでしょうか。
提案① Yoshi-kaから:「考えすぎる癖」と共に暮らすための5つの習慣
- 朝のスマホ断ち
- 朝日と運動
- 習慣化アプリ(Habitica)の活用
- 日記で感情の見える化
- 考えすぎることを“外に出す仕組み”を持つこと
考えすぎることの不安から働き方を選択してしまう人に5つの習慣を提案したいと思う。
共通点は”自分と向き合うルーティン”を作り出すこと。
自分と向き合うことは”余計に「考えすぎ」を増幅させるじゃないか”と思うかもしれない。
自分と向き合うことは、自分の中で”どこに折り合いをつけるか”を決める作業だ。
考えすぎのゴールを決める。考えすぎる人の”考え”にはゴールがないことが多い。
だから自分と向き合い、思考を整理することで、自分の中でゴールを決める。
折り合いをつける作業には”朝”が一番いいと思っている。朝活だ。
出勤する時間よりも1時間早く起きて、外に出る。
ただ玄関を開け、外を眺めるだけでもいい、ベランダ、デッキでもいい。
スマホを持たず、外に出て朝日を浴びる。そして自分と向き合う。
最初から完璧を求めてはいけない。5分でもいいから自分と向き合ってみる。
それが、ゴールを近づけてくれる。
考えすぎることを“外に出す仕組み”を持つことでゴールが見えてくる。
☆習慣化アプリ(Habitica)の活用、日記で感情の見える化、考えすぎることを“外に出す仕組み”を持つことについては後述する。
提案② AIから:不安を“選ぶ力”に変えるための行動設計
人間の「不安」は、本来、生存戦略の一部です。未来を予測し、最悪を避けるための感覚。
しかし現代においてその感覚は過剰になり、「選択肢が多すぎること」が逆に心を疲弊させる原因となっています。
“考えすぎる人”に必要なのは、「選ばないこと」ではなく、「選べる体力」を鍛えることです。
以下に、そのための行動設計を提案します。
1. タスク設計をNotionで見える化する
「頭の中で考え続けること」が不安を増幅させる最大の要因です。
思考は物理的な処理能力を消費するため、**視覚化による“思考の外在化”**は、脳のリソース節約に有効です。
Notionのような情報整理ツールで、日々のタスクを明示化・分類することで、“今、考えなくていいこと”を増やすことができます。
これは、思考過多な脳に「休憩スペース」をつくる行為です。
2. 自律神経を整える環境作り
「不安」という感覚は、脳だけでなく、身体が出しているアラートでもあります。
光・音・温度・香りといった五感にアプローチすることで、交感神経の過剰な興奮を抑えることが可能です。
例:
- 間接照明と朝日で光環境を整える
- ホワイトノイズや自然音で聴覚ストレスを軽減
- アロマやコーヒーの香りでリラックス状態を誘導
これらの環境整備は、身体と心を同時に“整える”仕組みとして機能します。
3. “選ぶ”という思考体力を鍛える
選択することには思考エネルギーが必要です。
特に、複雑な思考が得意な人ほど「選択疲れ」に陥りやすい。
そのためには、あえて選ぶ練習を日常に組み込むことが重要です。
例:
- 毎朝の服を3パターンから選ぶ
- メニューでは即決ルールを設ける
- 意識的に“決める”という行為を増やす
これにより、「自分は選んでも大丈夫」という内的信頼が蓄積されます。
4. 選択を減らすためのルールづくり
逆説的ですが、“選択肢を減らす”こともまた、選ぶ力を保つための戦略です。
例:
- 平日の朝は〇〇しかしない
- 作業開始前に深呼吸+水一杯を固定する
- スマホ使用は〇時〜〇時のみ
**ルールは自由を奪うのではなく、“自由を守る構造”**でもあります。
行動のテンプレートを持つことで、不安定な状況でも判断力を保つことが可能です。
「不安を消す」のではなく、「不安を“選ぶ力”に変える」。
それは、日々の小さな選択を積み重ねた先にしか、生まれないものなのかもしれません。
考えすぎる人におすすめの“環境を整えるツール”
| Notion | 考えすぎる人の“脳の外部化”ツール。タスクと感情の仕分けに最適 |
| Habitica | 習慣化が苦手なHSP・内向型におすすめの“ゲーミフィケーション思考” |
| ConoHa WING | 考えすぎる人こそ「ブログ」という逃げ場所を持とう。心の拠点に |
| 書籍『超訳 ブッダの言葉』 | 思考の“自動反応”を手放す。仏教×現代思考の実践書 |
・Habitica
とてもいいアプリケーションだと思う。特にゲームにハマった経験がある人なら尚更。
このアプリケーションの一番いいところは、”ゴールの見える化”にゲーム性を組み合わせているところだと思う。
ゴールの見える化×ゲーム。
考えすぎる人にとってゴールを決める・選択する・決断するというのは苦労が多い。
それを2Dゲームのような世界観が軽くしてくれる。
”入り口”を広くしてくれるんだ。
考えすぎる人にこそオススメしたいアプリケーション。
興味が湧いた方はこちら→公式サイト
・ConoHa WING
私も利用している。
ConoHa WINGのいいところは、サーバー利用料が安価で、WordPressでのサイト作成が、とても簡単に”あっという間に終わる”ところ。
実際簡単だった。
僕にもできたのだから、同じく考えすぎる”あなた”にもできる。
ConoHa WINGのおかげで、僕は今ブログを運営している。
考えすぎる人にこそ、発信の場は”必要”だ。
頭の中の”ぐるぐる”を外に出す必要がある。
その場所として”ブログ”が最適だ。
・書籍『超訳 ブッダの言葉』
この本は5回読み返した。
お釈迦様は元々王子だったという話はひとまず置いておこう。
この本を読んでから、”考えなくてもいいこと”を理解したと同時に、”考えなくてはいけないこと”が増えたと思う。
ただ単に考えなくてはいけないことが増えたわけではなく、考えることの”質”が上がるような感じ。
5回読んだとはいえ、まだまだ悟りを開くほど達観はできていない。
考えすぎる人にこそ読んでみて欲しい。
さらっと読める本になっているし、仏教に興味がない人でも読みやすい書籍だ。
まとめ:不安定な世界で、心の拠点をつくるという選択
この記事では、考えすぎる人の働き方について語った。
不安定な働き方、安定した働き方。
どちらを選択しても、不安からは逃れられない。僕の実体験だ。
考えすぎる人にとって選択が不安を呼んでくる。
僕は安定した臨床検査技師を辞め、発信者として生きていきたいと考えている。
そのためにブログ、YouTube、noteで発信している。
僕にとって発信することが、心の安定に繋がっている。
もしかしたら、考えすぎる”あなた”にも同じことが言えるかもしれない。
だから、朝日を浴びながら自分と向き合い、「自分らしさとは?」と自分に投げかけて欲しい。
AIに、考えていることをそのまま投げかけるのでもいい。
実体験だが、いいきっかけになると思う。
最後に
考えすぎる”あなた”に向けてこの記事を書いた。
このブログは、考えすぎる私の実体験を盛り込んでいる。真実だ。
考えすぎる自分に悩む”あなた”に届くと嬉しい。
記事を読んだ感想もお待ちしている。
AIについて調べれば、プロンプトがどうのとか、書いてあるが最初から上手くやろうとしないこと。
よく読まれている記事はこちらから





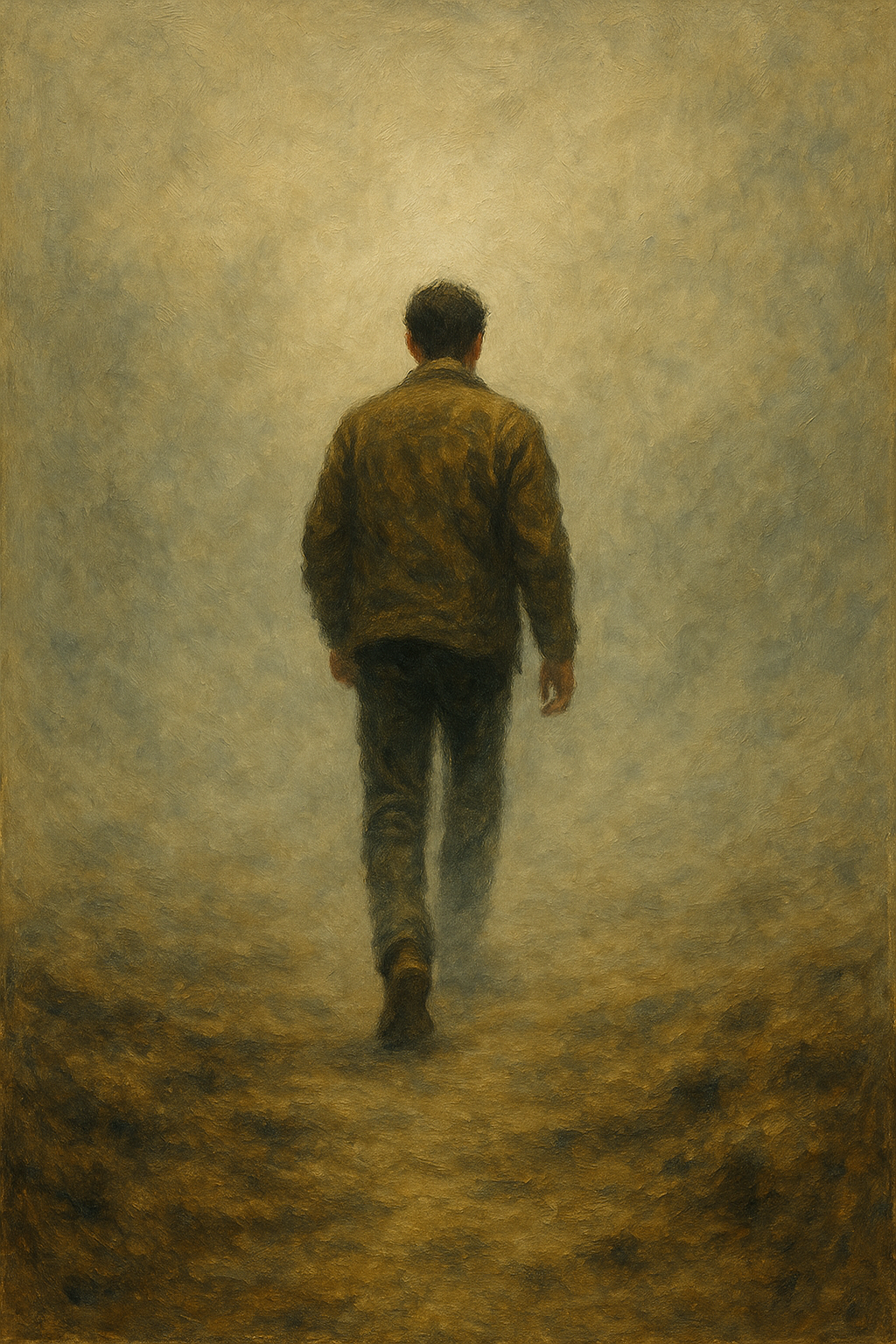
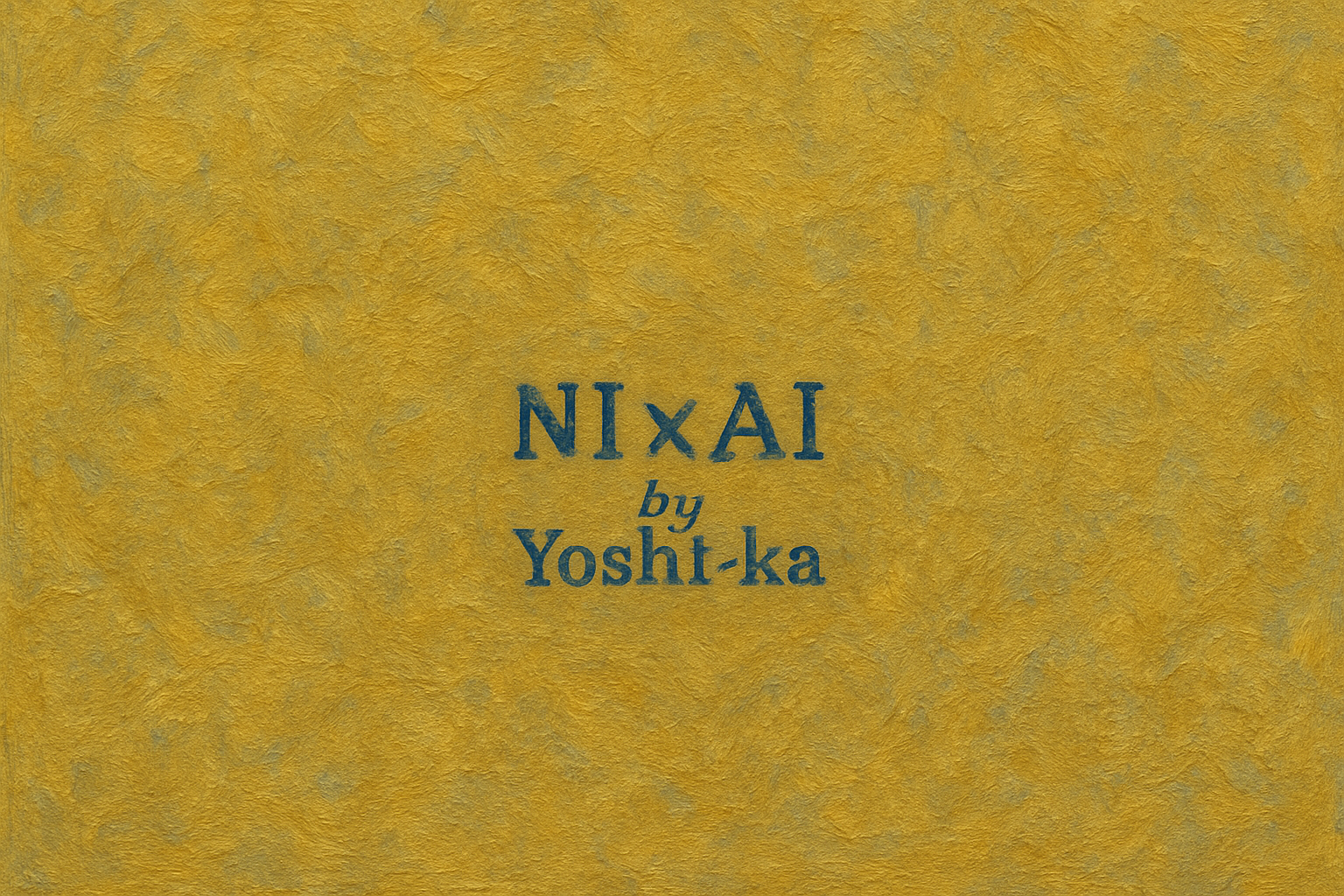
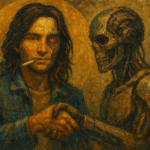


コメントを残す